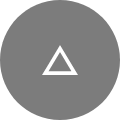2025年1月17日に、カンボジア・プノンペンにて企業による温室効果ガス(GHG)算定報告の推進に係るトレーニングワークショップを開催してまいりました。
本ワークショップは、日・ASEAN統合基金の下行われているPaSTI-JAIFプロジェクトの一環として、ASEAN地域の透明性強化を目指す活動として行われたものです。
本報告では特に2024年に行ったカンボジアにおける活動の概要をお伝えします。
カンボジアでの活動のはじまり
カンボジアで気候変動に係る透明性の推進は、産業廃水に関する活動量の情報が不足しているという政府からのニーズに基づいています。そこで、カンボジア大手の飲料工場に協力してもらい、産業廃水のデータ取得も含めたGHG算定報告をモデル事業として行うこととなりました。
カンボジアは企業から直接データを吸い上げるような取り組みの経験が乏しく、企業がGHG算定報告にどれだけの知識・理解があるのか、データをどの程度把握しているのか、報告できるキャパシティがあるのか、など一からカンボジア環境省および企業とすり合わせを行いながら進めてきました。

現地視察とデータ収集
国際協力事業を行っていていつも感じることですが、何事も現場を見て、実際に担当者のお話を伺ってみると見えてくるものがあります。
今回も、実際に工場を見学させていただき、GHG排出源の特定や、一歩進んで削減策の導入実績・見込みなども調査しながらGHGを算定するための自動計算ツール作成を行いました。なお、この企業は環境への意識が高く、飲料の製造過程で生じるメタンの回収や廃熱利用などもすでに行われており、しっかりとした環境対策が施された工場を持っています。一方で、ここまでの環境配慮をしながらも、GHG算定については全く経験がないというギャップも明らかになりました。

GHG算定トレーニングとこれからの活動
GHG排出量は活動量(どれくらい電気を使っているか、ガスを燃やしているかなど)に排出係数を乗じて求められます。2024年11月に行われたオンラインワークショップを経て、2025年1月のトレーニングでは、IPCCが設定している排出係数ではない独自の係数の使用やメタンの排出量と回収量の細かな数値の間違いの指摘など、技術的な議論・質問が多く挙げられたほか、データの計算ツールを学術的に授業で使用したいという声も上がり、大変活発で有意義なセッションとなりました。
今後は、算定をしたGHG排出量をどのように対外的に見せるかという、企業の価値の向上や投資を呼び込むという観点からのフォローも行っていく予定です。また、政府に対してはGHG算定報告制度の構築に向けて、各省庁の連携も含めた支援を引き続き行ってまいります。